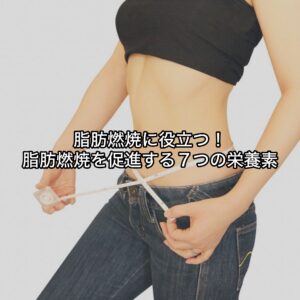リバウンド防止にプロテイン! もう太らないために

女性のダイエットにはプロテインが必要なのか?
その答えは個人差があるので一概には言えないですが、食生活や目的によっては必要もしくは必須になります。
プロテインが必要になる方は、
- タンパク質が不足している方
- 隠れ肥満(体重は標準でも筋肉量が少なく、脂肪が多い)
- 筋力向上や筋肉量アップをしたい方
- 激しい運動を頻繁にする方
上記の方も食事で改善出来れば無理にプロテインドリンクを飲む必要はありません。
すぐには食事の改善もしづらいのと、肉や魚を食べることや食事量を増やすのがきつい時にはプロテインドリンクで補うのも1つの対策です。
激しい運動をする方は基本的には必須になります。
ラグビーや高強度の筋トレをする方はその代償に筋肉へのダメージも多いので、体の主成分であるタンパク質を補給しましょう。
詳しくはこちらの記事に記載しています。

上記以外の方も、
- 健康のため
- 美容のため
- リバウンド防止など
以上の理由で日常からプロテインを飲んでいる方がいます。
なぜリバウンド防止のためにプロテインが必要なのでしょうか?
それは代謝低下に関係しています。
⒈リバウンド防止にプロテイン
ダイエットに成功したからにはリバウンドは避けたいところ。では、リバウンドしないためにはどうすればいいのか。
大事になってくるのは、以下の3つ
- 食事を急に変えないこと
- 運動や筋トレをやめないこと
- タンパク質を不足させないこと
①リバウンドの原因とは
極端な食事制限
ダイエットを始めるにあたってやりがちなのが「糖質制限ダイエット」などの何かを極端に制限する食事制限。これをすると体が飢餓状態になってしまいます。飢餓状態で食事を摂取した時に必要以上に体に溜め込んでしまいます。
代謝の低下
上記のような食事制限、生活習慣の乱れや加齢などが原因で代謝は下がっていきます。
特に女性は20代から緩やかに低下し、40代になると一気に低下していきます。
代謝が下がると消費できるカロリーが減るため、リバウンドしやすくなってしまいます。
②リバウンドを防ぐには
バランスの良い食事を心がける
食事を減らす場合は、夜ご飯だけ白米を半分にしてみる、間食をやめるなど。何かを極端に減らすのではなく食事全体の量と頻度を調節していきましょう。
筋トレをする
筋肉量の低下も代謝が下がる原因の1つです。筋トレをすることで筋肉量の低下を防ぎ、代謝が上がりやすくなります。
散歩などの有酸素運動も悪くはないですが、筋肉量は散歩ではつくことはほぼなく、むしろ落ちやすいので、筋トレがオススメです。
筋肉量を増やすのに必要なのがタンパク質。タンパク質は様々な食材に含まれているが、体内で合成することはできません。そのため食べ物から摂取する必要があります。食べ物から摂取しきれない分はプロテインなどで補っていきましょう。
プロテインを飲む
ダイエット成功後は運動量が落ちてしまいがち。
そうするとせっかくついた筋肉も落ちやすくなります。
そうすると上記のリバウンドの原因でも述べた代謝の低下に繋がります。
代謝の低下や筋肉量の低下を防ぐためにもプロテインを飲みましょう。
痩せる→健康にシフトがリバウンド防止のポイント
痩せるためのダイエットの食事→健康的な食事に切り替えるべきなのですが、頑張った反動で痩せる前の食生活に戻ってしまう方も多いです。
そうすると糖質や脂質の多い食事を摂りあっという間に元通りに、、。
また痩せるためのきついトレーニング→太らない定期的な運動に切り替えたいところがパッタリとやめてしまったり、、。
リバウンド防止のポイント
- バランスの良い健康的な食事を摂る
- 筋トレを継続して行う
- プロテインを飲んで代謝低下を防ぐ
2.タンパク質を摂る基準値
1日の必要タンパク質量(g)=体重(kg)×体重1kgあたりのタンパク質必要量(g)
日本人の食事摂取基準によると、1日に必要なタンパク質は摂取エネルギーの13〜20%が理想とされており、成人女性だと50gが1日の推奨量とされています。
また、筋肉をつける時は体重の1.5〜1.8gのタンパク質が必要と言われています。
しかし、これはあくまで推奨例であり、体重や筋肉量、運動量などに伴い個人差があります。
下の数値を基準に1日の必要なタンパク質を上の式から求めてみてください。
体重1kgあたりのタンパク質必要量(g)
- 活発に活動していない人・・・0.8
- 週に1〜2回、30分の筋トレや軽い運動・・・0.8〜1.1
- 持久性トレーニング・・・1.6〜1.7
- 高強度の筋トレ・・・1.2〜1.7
例) 60kgで週に1−2回の軽い運動をしている方は60gのタンパク質を1日の目安に摂取しましょう。
3.オススメの高タンパクな食材
高タンパクな食品類として挙げられるのは主に以下の5つ
- 肉類
- 魚介類
- 卵類
- 大豆製品
- 乳製品
さらに詳しく中身を見ていきましょう。
①肉類(100gあたりタンパク質含有量)
生ハム(24.0g)、鶏ささみ( 23.0g)、牛もも肉(21.2g)、ウインナー(13.2g)
②魚介類(100gあたりタンパク質含有量)
イワシ丸干し(32.8g)、いくら(32.6g)、焼きたらこ(28.3g)、するめ(69.2g)
③卵類(100gあたりタンパク質含有量)
卵黄(16.5g)、ゆで卵(12.9g)、生卵(12.3g)
④大豆製品(100gあたりタンパク質含有量)
きな粉(35.5g)、納豆(16.5g)、豆腐(6.6g)、豆乳(3.6g)
⑤乳製品(100gあたりタンパク質含有量)
パルメザンチーズ(44.0g)、ヨーグルト(4.3g)、牛乳(3.3g)
商品によって差があるため成分表記で確認しつつタンパク質を摂っていきましょう。
4.おすすめのプロテインと選び方
上記にもあるようにタンパク質は毎日の食事で摂るのがベストです。しかし、食事から目安量まで摂ることが難しい場合はプロテインなどで補っていきましょう。
プロテインにも種類があるためそれぞれの違いを把握した上で自分に合ったプロテインを選んでいきましょう。
〜プロテインの種類〜
①ホエイプロテイン
- 牛乳から精製されるプロテインパウダー(牛乳中20%がホエイ)
- 吸収が速い
- 筋肉の合成に有効な必須アミノ酸やBCAAが豊富で体内での利用効率が良い
※ホエイとは乳製のこと
②ソイプロテイン
- 大豆を原料としているプロテイン
- 吸収は比較的ゆっくり
- 代謝をサポートし、血液をサラサラにするアルギニンが豊富
③カゼインプロテイン
- ホエイと同じく、牛乳から作られるプロテインパウダー(牛乳中80%がカゼイン)
- ゆっくり吸収され、長期間補給可能
- 運動している方に有効なアミノ酸、グルタミンが豊富
吸収の速いホエイプロテインは吸収が速い上に、体内で利用される量も多いことから運動後や体作りにおすすめです。
ソイプロテインやカゼインプロテインは穏やかな吸収で持続的な栄養補給が可能です。
ダイエットの間食や就寝前に取り入れて空腹を満たすのにおすすめです。
また、プロテインに飲みにくさを感じている方は、水に溶けやすいホエイプロテインやプロテインバーを活用するのもおすすめです。
しかし、プロテインバーは脂質や炭水化物がプロテインパウダーに比べ多く入っているため成分表記をしっかりと確認しましょう。
〜おすすめのプロテイン〜
・SAVAS
コンビニなどでも見かけるプロテイン。手軽に手に入るので試しに飲んでみるのもアリだと思います。
また、コンビニでは見かけないフレーバーもあるので、ネットで調べてみてください。
・VALX
ソイプロテインは水に溶けにくい性質のため飲みにくさを感じる人も多いです。
VALXは溶けやすさに力を入れているため、ソイプロテインの中でも飲みやすいです。
・森永製菓inシリーズ
最後はプロテインバーのおすすめを紹介していきます。
inシリーズはクランチチョコタイプのみだけでなく、ウエハースタイプがあったりなど種類が多いです。
脂質を抑えたプロテインバーもあります。
5.タンパク質を摂る上での注意点
最後にタンパク質を摂る上での注意点を紹介していきます。
タンパク質は摂り過ぎも良くありません。どのような影響があるのか紹介していきます。
・腎臓への負担が大きくなる
タンパク質を摂取すると、体内で合成、分解が行われます。
その過程で、必要以上に摂取したタンパク質は分解されていきます。
分解されて窒素になったタンパク質は、肝臓、腎臓の働きによって排出されていきます。
窒素はアンモニアに変換されますが、このアンモニアは人体にとって有害で、腎臓に必要以上に負担をかけてしまいます。
タンパク質を摂取しすぎることでその分、多くのタンパク質を分解し、アンモニアにしなければならないため、内臓に負担がかかってしまいます。
・皮下脂肪として蓄積される
タンパク質を食品から摂取する場合、肉や魚、卵など動物性のタンパク質だと高カロリーな内容になってしまいます。
沢山食べてタンパク質を摂取することも大切ですが、食事内容によってはカロリーオーバーになってしまうため注意が必要です。
脂質の少ない食品を選んだり、大豆類やブロッコリーなどの植物性のタンパク質も取り入れるなどしてみましょう。
・腸内環境が乱れる
腸内には善玉菌と悪玉菌、さらに中間の菌があり、善玉菌の数はごく僅かです。しかし、タンパク質を必要以上に摂取すると、体内に吸収されなかったタンパク質が腸内までそのまま届き、悪玉菌の餌になってしまいます。
タンパク質を食べた悪玉菌は増殖し、中間の菌や善玉菌の働きを邪魔します。これによって腸内の活動が鈍くなり、腸内環境が乱れてしまいます。
6.まとめ
リバウンドを防ぐには代謝を上げることが大切です。代謝を上げるには筋肉量を上げる必要があります。
その上で大切なのが筋肉を作るタンパク質といった関係性が分かってきたと思います。
食事として摂りきれない場合にプロテインなどで補っていきましょう。
プロテインは飲み続けることができるか、コスト面に問題はないかなど自分にあったものを選んでいきましょう。
ビギナーフィットネスFIRST 蒲田店 栗田

ビギナーフィットネスFIRSTのSNS
公式LINE:https://lin.ee/lEng7MY
Instagram:first0917
Youtube:https://youtube.com/channel/UC0YX-j4X-OgpJaTfH91X-HA